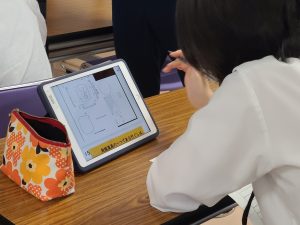ワクワク考古楽IN霧島市立国分南中学校
令和6年5月17日の5・6校時,国分南中学校でワクワク考古楽(出前授業)を実施しました。
今回のワクワク考古楽は一年生を対象に,国分南中学校が毎年夏休みに行っている「上野原遺跡ボランティアガイド」の経緯や活動の様子と,国指定史跡上野原遺跡について学習しました。
ボランティアガイドは平成11年から始まり,今年で26回目を迎えます。まだ上野原縄文の森ができていない頃の活動の様子をテレビニュースで特集されたビデオを観たり,中学時代に実際にガイドに参加していた職員(国分南中卒業生)の生の声を聞いたりしました。また,最近の活動の様子についても写真を見てもらいました。
生徒たちのほとんどは上野原縄文の森に行ったことがありましたが,国分南中が長くボランティアガイドをしていたことは知らなかったようで,先輩たちの活動を熱心に見ていました。
次に,上野原遺跡はどんなところがすごいのかについて学習しました。上野原遺跡からは約10,600年前の国内最古・最大級の集落跡が発見され国指定史跡になっていることや,約6,000年前の対で埋められた壺形土器を中心に祭祀が行われた場所が発見され,そこから出土した土偶や耳飾りなど767点が国の重要文化財に指定されていることなどを紹介すると,生徒たちは興味深く耳を傾けていました。
また,南九州の縄文土器の特徴として,底が平らで口の部分の形が四角やレモン形のものがあることや,縄ではなく貝殻で文様をつけていることなどを話しながら本物の土器を見せると,身を乗り出して興味深く見ていました。
6時間目は外で火おこし体験を行いました。友達と協力しながら,楽しんで火おこしをすることができました。
今年の夏休みも,たくさんの生徒がボランティアガイドに是非参加してほしいです。
ワクワク考古楽出前授業in国分南小学校
令和6年4月19日(金),霧島市立国分南小学校の6年生88人に,「ワクワク考古楽」出前授業を実施しました。
今回は,総合的な学習の時間で,縄文時代について紹介しました。国分南小にとても近い遺跡である上野原遺跡では,多くの竪穴建物跡などの遺構が発見され縄文時代のムラの跡であることから,国の史跡になっていること,土器や石器など767点の遺物が重要文化財になっていることなどを説明しました。
子どもたちは,全国的に注目された遺跡が身近にあることにびっくりしていました。また,火山に囲まれた生活や,南公園近くで貝塚が見つかっていることから,海岸線が現在と異なる位置にあったことにも驚いていました。
特に縄文時代の衣食住について,発掘調査から分かったことを紹介すると,集中してメモしながら聞いていました。
次に,実際に出土した土器や石器に触れる時間では,興味津々に説明を聞き,石器の使い方について考えることができました。また,石器を触れる際,両手で大事そうに扱う様子が印象的でした。
今後は,上野原縄文の森に見学へ行き,調べ学習を進めていくそうです。今回の授業を通して,縄文時代や当時の人々の生活についてさらに「知りたい」という意欲をもち,学習を深めるきっかけになればと思います。
南の縄文文化発信事業(ワクワク考古楽)学習指導案(PDF)
|
|
ワクワク考古楽出前授業(薩摩川内市立鹿島小学校)
2月9日(金),薩摩川内市立鹿島小学校の5・6年生に,ワクワク考古楽出前授業を実施しました。
授業では,甑島を代表する二つの遺跡,「中町馬場遺跡」と「大原・宮薗遺跡」について紹介しました。
中町馬場遺跡は上甑島の里にあります。発掘調査や地質研究の成果をもとに,山から流れる土砂と海の沿岸流の作用により,土砂が堆積して里の平地ができたことを伝えました。中町馬場遺跡では,弥生時代・古墳時代の貝溜まりや人骨,多量の貝や動物・魚などの骨が出土したことや,発掘調査に当時の里小学校の児童が直接参加したことなど紹介しました。
次に,鹿島小学校と同じ下甑島の南端の手打集落にある大原・宮薗遺跡の発掘調査成果を紹介しました。弥生時代の壺棺から,幼児の人骨が出土したことなど,中町馬場遺跡同様に重要な遺跡であることを説明しました。
また,中町馬場遺跡出土の人骨や動物の骨,魚骨,大原・宮薗遺跡出土の土器などを実際に見てもらい,触感や重さを実感してもらいました。
そのあとは,全学年の子どもたちに,火起こし体験を挑戦してもらいました。
まず始めに,道具やその使い方を説明し,子どもたち同士ペアになって火起こしをしてもらいました。火が着いたときは,喜んでいました。
子どもたちは授業中,目を輝かせながら,大きくうなずきながら,説明を聞いてくれました。この授業を通して,甑島の歴史についてさらに興味をもち,郷土理解を深めてくれたと感じることでした。
ワクワク考古楽出前授業(霧島市立国分小学校)
1月24日,霧島市立国分小学校の6年生(4クラス138人)で,ワクワク考古楽出前授業を実施しました。
国分小学校の建っている場所は,島津義弘が築いた舞鶴城跡であると共に,本御内(もとおさと)遺跡という,縄文時代から近代までの複合遺跡です。
今回の出前授業では,平成29年度に行った発掘調査の成果を紹介しながら,どのような遺構や遺物が見つかったのか紹介しました。
子どもたちは,発掘調査の写真を見ながら,遺跡についての理解を深めることができました。
授業の後半では,実際に本御内遺跡から出土した土器や石器,古代の瓦,陶磁器類を展示し,手に取って重さや感触を確かめていました。また,タブレットを使って遺構や遺物の3D体験を楽しみました。
子どもたちの感想
- 何千年も前の遺跡や土器・石器などが,霧島市にたくさんあることが分かりました。
- 実際に出てきた土器などをさわりました。普段はめったにさわれないものなので,貴重な体験でした。
- 国分小学校の周辺の歴史を知ることができた1時間でした。また,ほかの機会があれば,自分でも調べてみたいなと思いました。
本御内遺跡報告書(PDF)
『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(199)「本御内遺跡」
ワクワク考古楽出前授業~宮之城中学校(さつま町)~
12月20日,さつま町立宮之城中学校で,『ワクワク考古楽』 を1年生(155人)に向けて実施しました。宮之城中学校は「虎居城」という中世の山城跡の中に建っています。現在,当センターでは虎居城跡の一角を発掘調査しています。
天気が良ければ,現地見学を予定していましたが,あいにくの雨となりました。そこで授業では,まず,埋蔵文化財センターの仕事について紹介した後,虎居城とその周辺の地形の成り立ち,虎居城の歴史について説明しました。
次に,虎居城跡の実際の写真を提示しながら,発掘調査で見つかった,「曲輪」・「切岸」・「堀切」・「竪堀」・「横堀」・「虎口」といった「山城」の特徴的な遺構を説明しました。
最後に,中世の陶磁器や近世の瓦などの実物を見たり,実際に手にしたりする活動を通して,歴史を実感してもらいました。
この体験が,今後の学習意欲や,地域の歴史理解につながればありがたいです。

吾平小学校の遺跡見学
10月3日,鹿屋市立吾平小学校6年生の児童32人と引率の先生方が,授業の一環として名主原遺跡(鹿屋市吾平町)見学に訪れました。
まず初めに,調査担当の職員が遺跡の概要について説明しました。児童たちは社会科(歴史)の授業で習ったことを思い出しながら聞いていた様子でした。
その後,2グループに分かれて,遺跡見学と発掘体験を交互に行いました。
遺跡見学では,まず,地層の学習を行いました。代表的な火山灰層について,それが何年前に降り積もったのか,何時代に当たるのかを説明を聞きました。児童も理科の学習で地層の成り立ちについて学んでいたので,興味深く聞いていました。
次に,建物跡について学習しました。名主原遺跡では,古墳時代の竪穴建物跡が多数見つかっています。完全な形に近い,大きな土器が残っている建物跡もあり,当時の生活を感じることができたようです。また,その建物跡を掘る作業員さんの細やかな作業も直接見ることができました。
発掘体験では,作業員さんに掘り方を教わりながら地面を少しずつ削って土器を探しました。すぐに見つけた児童も多く,楽しみながら体験できました。
最後に,埋蔵文化財センターの職員が児童に向けて,どうしてこの仕事に就いたかを紹介しました。高校時代に考古学に興味を持ったことや進路について自分で調べて大学を探したこと,どんな勉強が必要だったかなどを話しました。
児童からは「遺跡をみたら土器がいっぱい出ていて,また建物跡もたくさんあって,びっくりした」,「発掘体験で土器が見つかったとき,とてもうれしかった」という感想が聞かれました。
今回の体験が,児童の学習はもとより地域理解や今後の進路選択に役立ち,未来の考古学者のタマゴが育っていたら何よりもうれしいことだと思います。
|
|
|
|
|
|

竪穴建物跡から炭が多く見つかっており,建物が燃えたかもしれないことを説明しました |
|
|
|
|
|
|
|
|
ワクワク考古楽出前授業in鹿児島盲学校
7月11日,鹿児島県立鹿児島盲学校でワクワク考古楽を実施しました。今回は,「発掘調査の方法や西南戦争の遺跡の発掘調査成果を知ろう」という学習課題をもとに,授業を行いました。
はじめに,埋蔵文化財センターの業務について紹介しました。発掘調査の方法を紹介するとともに,その成果が世界遺産や国の史跡の指定に役立っていることを説明しました。
次に,西南戦争時の西郷軍と政府軍の進路と,関連する「滝ノ上火薬製造所跡」,「高熊山激戦地跡」,「チシャヶ迫堡累群跡」,「岩川官軍墓地」の発掘調査の調査成果を紹介しました。
最後に,発掘調査で見つかった遺物に触れる活動を行いました。西南戦争で使われた本物の銃弾のほか土器・石器にふれ,手触りや重さを体感しました。
生徒たちは今回の授業を通して,地域の歴史や先人たちの活躍を理解することができたと思います。これからも,いろいろな活動を通して地域のことを学んでもらいたいと思いました。
|
|
|
|
|
|
ワクワク考古楽inさつま町立柏原小学校
6月29日,さつま町立柏原小学校の4・5年生でワクワク考古楽を実施しました。令和3年度から実施している「廃寺は語る! 鹿児島の仏教文化事業」の一環で,今年度は同校区内に位置する大願寺跡の発掘調査を行いました。
今回のワクワク考古楽では,その発掘調査成果や大願寺がどのような寺であったのか紹介する授業を行いました。
大願寺は脇寺が12もある大きな寺院であったこと,室町時代の征夷大将軍足利義満自筆の木扁額(もくへんがく)「医王宝殿」が掲げてあったことを紹介すると,とても驚いていました。また,発掘調査において,江戸時代のものから一番古いもので縄文時代早期の遺物が出たことにも,興味をもっていました。
最後に大願寺跡で実際に出土した押型文土器や石斧,同じさつま町内に位置する中世の山城「虎居城跡」で出土した大願寺と同時期の中世の陶磁器や土師器,そして火鉢などを,手に取って触れる活動を行いました。現代で使用している食器等と中世の遺物を見ながら,形や大きさ比較して感想を述べることができていました。
子どもたちは今回の授業を通して,自分の住んでいる地域に多くの文化財が残っており,8,000年以上も前から自分たちの祖先がこの地に住んでいたことに,大変驚いていました。自分たちの住んでいる地域の歴史について考える良い機会となりました。
|
|
|
|
ワクワク考古楽in肝付町立宮富小学校
令和5年5月29日,肝付町立宮富小学校の6年生にワクワク考古楽を実施しました。今回のワクワク考古楽では,「かごしまの古代について知ろう」というめあてを立てて授業を行いました。
奈良時代,聖武天皇の「国分寺建立の詔」に基づいて,鹿児島県内でも薩摩国分寺と大隅国分寺が建立され,その場所や発掘調査からわかったことを説明しました。また「隼人」についても触れ,朝廷による支配や「隼人の役割」についても紹介しました。子どもたちは,興味をもって頷きながらきいている様子が見られました。
さらに,近隣の久保田牧遺跡(鹿屋市吾平町)の調査の成果から,古代の遺構・遺物が見つかっていることを紹介しました。身近な地域で古代の人々のくらしの跡が見つかっていることに驚いていました。
その後,実際に遺物に触れる時間を設定しました。大隅国分寺出土の瓦や久保田牧遺跡出土の墨書土器・刻書土器を手に取って観察しました。子どもたちは,瓦の重さや大きさに驚いていました。また,墨書土器にはどのような字が書いてあるのかじっくりと観察する様子が見られました。さらに古い時代の縄文土器や弥生土器も紹介し,手触りや特徴を実感することができました。
これから学習が進み,古代の学習をする際には,今回の授業内容を思い出し,教科書に記載されている事柄に加えて,大隅半島にも古代の生活が広がっていたことを感じてほしいと思います。
|
|
|
|
ワクワク考古楽出前授業in枕崎市立枕崎小学校
6月19日,枕崎市立枕崎小学校で「ワクワク考古楽」を実施しました。
今回は「縄文時代のくらし」をテーマにして授業を進めました。
縄文時代の人たちは,狩猟・漁労・採集などで食生活をしていたこと,住居は竪穴建物に住んでいたこと,土器や石器などの道具を使っていたことなどを紹介しました。
次に,なぜそのような「昔のこと」がわかるのか,発掘調査の成果をもとに説明しました。鹿児島の地層には過去の火山灰層がいくつも含まれており,その火山灰層の年代から建物跡などの「遺構」,土器や石器などの「遺物」の時代がわかることを紹介しました。
続いて,本物の土器や石器に触れる活動を行いました。鹿児島の縄文土器の文様は「縄」ではなく「貝」で付けたのもが多いことに驚いていました。児童たちは石斧や磨石などは,何に使ったのか,どのように使っていたのか,興味深く手に取っていました。
最後に,枕崎小学校近辺の遺跡を紹介しました,自分たちが住んでいる地域にも多くの遺跡があることを知り,感慨深げにしていました。
|
|
|
|
|
|