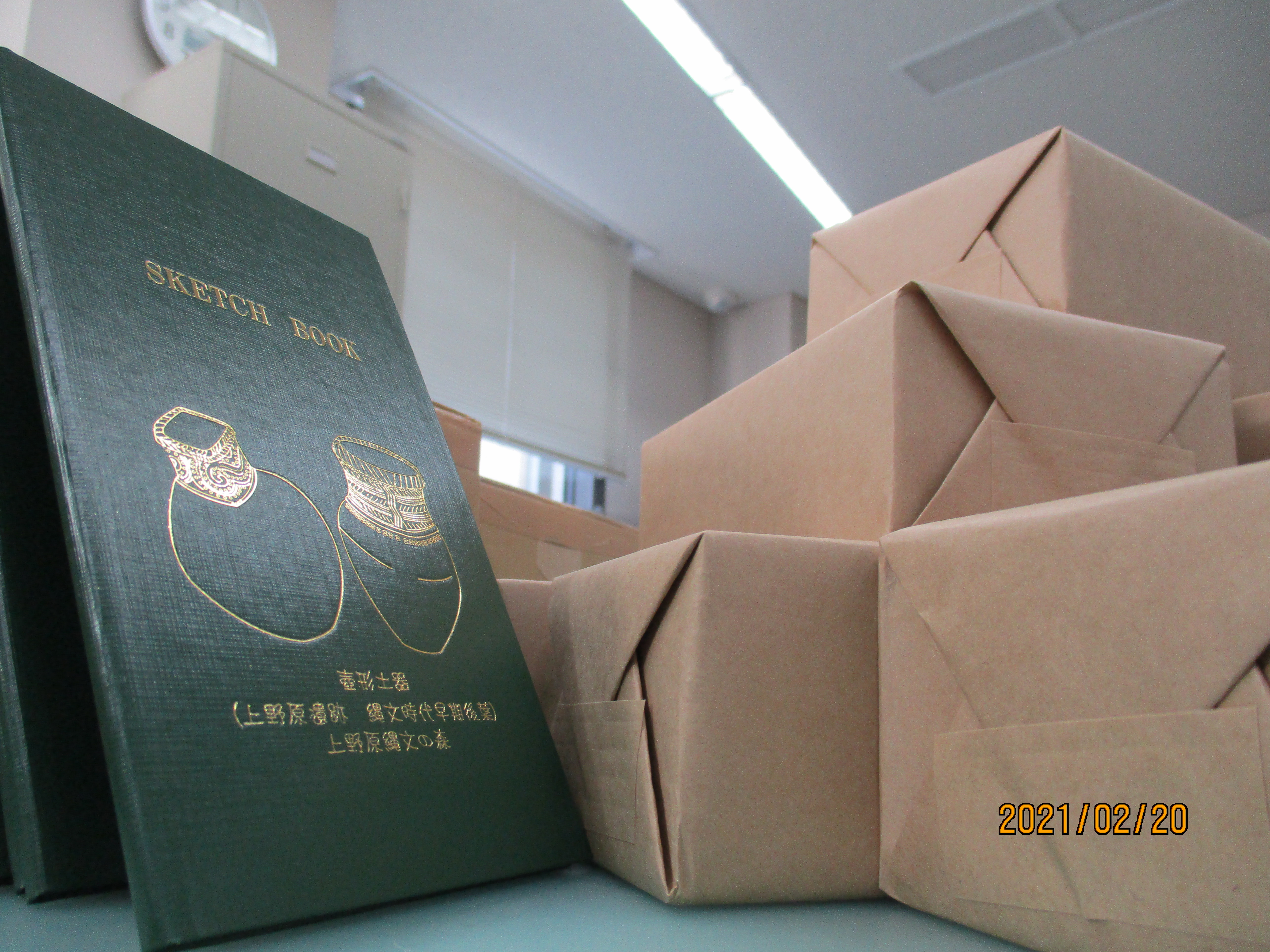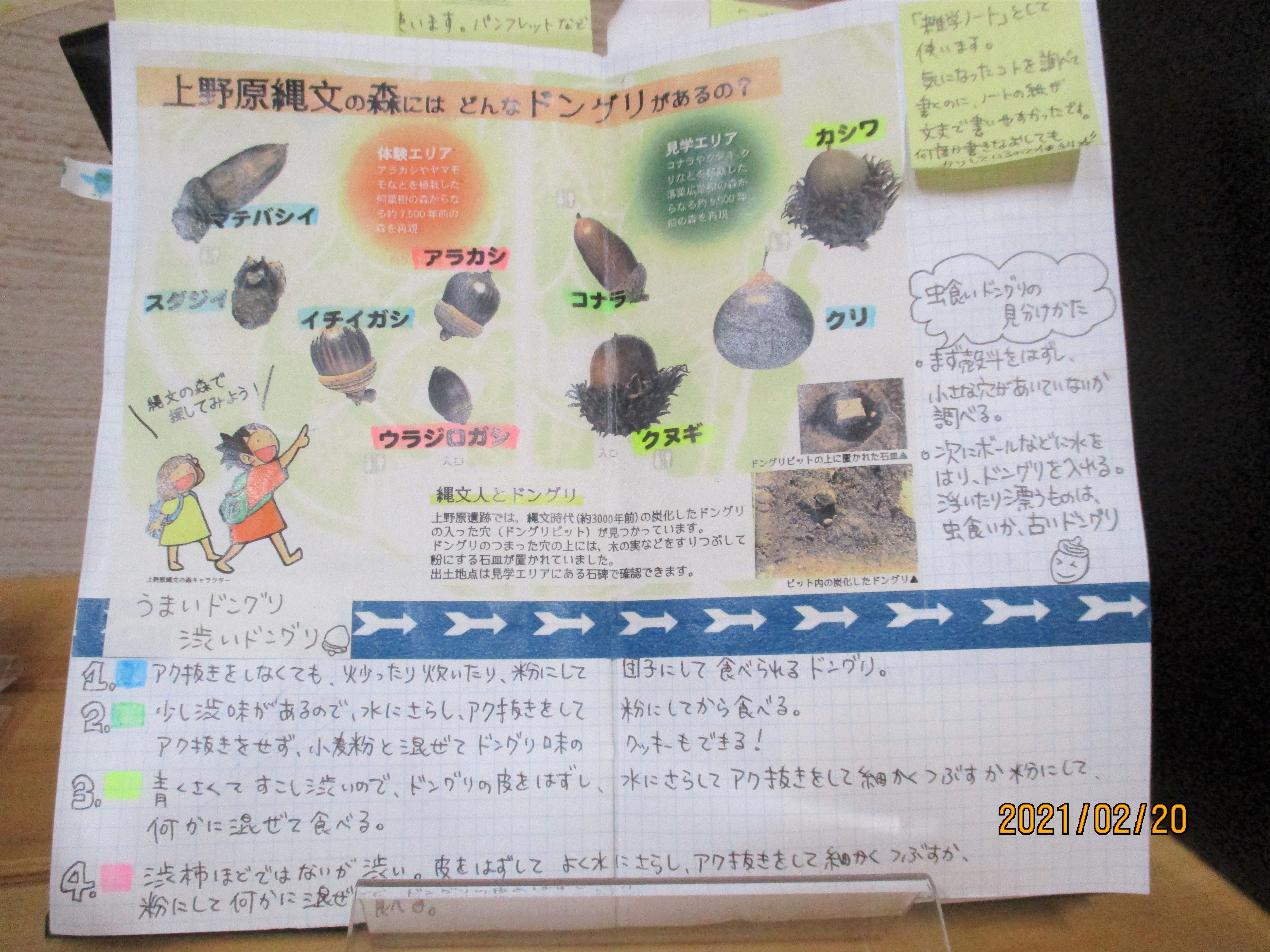鹿児島城跡の調査が南日本新聞に紹介されました
鹿児島城跡の調査が南日本新聞に紹介されました。
詳しくは,以下のリンクをご覧ください。
どんぐりイベント「ふれあい体験」中止のお知らせ
3月20日(土)実施予定のどんぐりイベント「ふれあい体験」は
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,開催を中止いたします。
どうぞご理解くださいますようお願いいたします。
アートギャラリー「ふたりの切り絵展」開催中!
野帳入荷のお知らせ
【お知らせ】第59回企画展講演会について
2月27日に開催予定の第59回企画展講演会は,予定通り開催致します。
現在開催中の第59回企画展「海と活きた古代人 ~旧石器時代から弥生時代の鹿児島~」に関連した講演会を行います。
※「きりしま歴史散歩」と共催
【日 時】令和3年1月16日 午前10時から正午→令和3年2月27日(土)午前10時から正午に変更
【講 師】稲田 孝司 氏(岡山大学名誉教授),木下 尚子 氏(熊本大学名誉教授)
【定 員】100人程度(要事前申込み)
【資料代】100円
【場 所】 霧島市国分シビックセンター 多目的ホール
〇問い合わせ・申込先
〒899-4318
鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号
上野原縄文の森 事業課
電話 0995-48-5701
FAX 0995-48-5704
メール uenohara@jomon-no-mori.jp
申込フォームはこちら